「Webサイトを作ってみたけど、なんかデザインがしっくりこないな…」
そんなふうに感じたこと、ありませんか?
ただ、私も最初は「Webフォントってそもそも何?」「どうやって使えばいいの?」と戸惑っていました。
この記事では、私が実際に調べて理解していった流れをもとに、Webフォントの基本の仕組みや導入の方法、
そしてよく使われているサービスまでを、できるだけわかりやすくまとめました。
私自身、最初はMacでデザインしたサイトをWindowsで開いたとき、
「え、同じCSSなのに見た目が違う…」と戸惑ったことが何度もありました。
それをきっかけに、Webフォントを使い始めたんです。
フォントが変わるだけで、デザインの完成度が一段上がる感覚がありました。
この記事では、Webフォントの仕組みや選び方、導入の流れ、
そして実際に使ってみて感じた注意点までをまとめています。
初心者の方でも読めるように、できるだけ実感を交えて書いていきます。
Webフォントとは
Webフォントとは、インターネット上のフォントデータを読み込んで文字を表示する仕組みのことです。通常、フォントはユーザーの端末にインストールされている「システムフォント」で表示されます。
しかしこのシステムフォントは、OSごとに異なるのが難点です。
たとえば、macOSでは「ヒラギノ角ゴシック」が標準フォントですが、
Windowsでは「游ゴシック」や「メイリオ」が使われています。
この違いにより、同じCSSで指定しても文字の太さや行間、全体のバランスが微妙に変わることがあります。
結果として、Macではスタイリッシュに見えていたデザインが、Windowsで見ると「なんだか間延びして見える…」というようなズレが起こるんです。私も最初、MacでデザインしたサイトをWindowsで確認したとき、「フォント変えた覚えないのに、雰囲気が全然違う!」と驚いたことがありました。それ以来、Webフォントを使うようにしています。
Webフォントを導入すれば、どの環境でも同じ書体を表示できるため、デザインの再現性が高まり、ブランドや世界観を正確に伝えやすくなります。「フォント崩れを防ぐためのCSS対策」としても有効です。
webフォントを使用するメリット・デメリットとは?
Webフォントのメリット
①どの端末でも同じフォントで表示できる
Webフォントを使う一番の魅力は、どんな端末でも文字の見た目が変わらないこと。MacでもWindowsでも、スマホでもタブレットでも、同じフォントで表示されます。
私も最初は「自分のPCではきれいに見えるのに、別の端末だとなんか違う…」ということがよくありました。それがWebフォントを導入してから、どこで見ても同じ印象に揃うようになって、デザイン全体がぐっと安定したように感じました。
特に企業サイトやポートフォリオのように、ブランドの印象を大事にしたい場合には“どんな環境でも同じ見え方を保てる”というのは本当に強みです。
②デザインの幅が広がる
Webフォントを使うと、選べるフォントの数が一気に増えます。和文・欧文を合わせると本当に数千種類。
ナチュラル、スタイリッシュ、かわいい、かっこいい——どんなテイストのサイトにも合う書体が見つかります。
私が初めてGoogle Fontsを触ったときも、「こんなに無料で使えるんだ!」と感動しました。サイトの雰囲気に合わせてフォントを変えるだけで、「おしゃれ感」「信頼感」「柔らかさ」などが全然違って見えるんですよね。デザインの完成度をあと一歩上げたいとき、フォントは意外と大きな武器になります。
③読みやすさを調整できる
Webフォントは、見た目の印象を整えるだけでなく「読みやすさ」にも効果的です。見出しは太めで存在感のあるフォント、本文はシンプルで読みやすいフォントにするなど、役割ごとにフォントを分けるとサイト全体がぐっと見やすくなります。
私はブログを書いているとき、本文のフォントを変えただけで「なんか急に読みやすくなった!」と感じたことがあります。
文字って、思っている以上に“デザインの空気”を変えるんですよね。
Webフォントのデメリット
①表示が遅くなることがある
Webフォントは外部からデータを読み込む仕組みなので、フォントの種類や太さをたくさん指定すると、ページの読み込みが少し遅くなることがあります。特に日本語フォントは容量が大きめなので、モバイル環境だと注意が必要です。
私も一度、見出しと本文の両方に別フォントを設定していたら、読み込みにワンテンポかかってしまって、「あ、これか…!」と実感しました。それ以来、必要なウェイトだけに絞って読み込むようにしています。
②ライセンスに注意が必要
フォントによっては、商用利用NGだったり、有料ライセンスが必要なケースもあります。「無料でダウンロードできた=自由に使える」ではないので、使う前に利用規約をチェックするのが大事です。
私も昔、クライアント案件で指定フォントを調べたら商用不可だったことがあり、急いで別のフォントを探し直した経験があります。Google FontsやAdobe Fontsのようにルールが明確なサービスを選んでおくと安心です。
③使いすぎるとバランスが崩れる
フォントを探していると楽しくなって、ついあれもこれも試したくなります。でも、種類を増やしすぎると全体の統一感がなくなってしまうんです。
私も最初の頃、3種類くらいのフォントを使って「にぎやかすぎる…」と後悔したことがありました(笑)基本は「見出し用」と「本文用」の2種類で十分。同じフォントの中で太さを変えるだけでも印象が変わるので、それだけで十分変化をつけられます。
Webフォントの導入方法(HTML・CSS)
Webフォントを使うには、大きく分けて 「外部サービスを利用する方法」 と 「自分でフォントを用意してサーバーに置く方法」 があります。私が試してみて「これが一番シンプルだった」と感じたのは、Google Fontsを使う方法です。無料で使えて、コピペするだけで導入できるので、初めての方でもすぐ試せます。
Google Fontsを使う方法
- Google Fontsのサイトを開く
- 使いたいフォントを選ぶ(例:「Noto Sans JP」など)
- 太さ(ウェイト)を選ぶ
→ Regular(400)や Bold(700)など、必要なものだけ選ぶと読み込みが軽くなります。 - 表示されたコードをコピーして、HTMLの
<head>に貼り付ける - CSSで指定する
body {
font-family: "Noto Sans JP", sans-serif;
}
これだけでOKです。
私も最初は「そんな簡単なわけないよね?」と思ってたんですが、本当に貼るだけで反映されました(笑)
もし反映されない場合は、笑ブラウザのキャッシュをクリアしてリロードすると直ることが多いです。
Adobe Fontsを使う方法
Adobe Creative Cloudを使っている方なら、追加費用なしでAdobe Fontsも使えます。
サイト上で使いたいフォントを選んで「Webプロジェクトを作成」し、発行されたコードをHTMLの<head>に貼り付けるだけ。
<link rel="stylesheet" href="https://use.typekit.net/xxxxxx.css">
私はIllustratorやPhotoshopで使っているフォントをWebでも統一したかったので、この方法をよく使っています。デザインの一貫性を保てるのが便利なんですよね。
自分でフォントを用意して使う方法(少し上級編)
もう少し慣れてきたら、自分でダウンロードしたフォントファイル(.woffや.ttfなど)をサーバーにアップロードして使う方法もあります。こちらは少し上級者向のやり方です。
@font-face {
font-family: "MyFont";
src: url("fonts/myfont.woff2") format("woff2");
}
ただし、この方法はライセンス確認が必須です。商用利用がNGなフォントも多いので、私は念のため、仕事ではGoogle FontsかAdobe Fontsしか使っていません。
Webフォントがうまく表示されないときの原因と解決策
Webフォントを導入してみると、最初はうまくいっても「文字が一瞬消える」「違うフォントで表示される」など、
ちょっとしたトラブルがよくあります。私が実際に経験してわかった“つまずきポイント”とその解決策をご紹介します。
① フォントが一瞬消える(FOUT・FOIT問題)
Webフォントを読み込むタイミングによって、文字が一瞬消えたり、別のフォントで一瞬表示されたりする現象があります。
日本語フォントのように容量が大きい場合ほど起こりやすいです。
私が試して一番効果を感じたのは、CSSで font-display: swap; を設定する方法。
これを指定しておくと、フォントが読み込まれるまで一時的にシステムフォントで表示してくれるので、「文字が消える」現象がほとんどなくなりました。
② 思っていたフォントと違う書体で表示される
Webフォントが反映されていないときは、まずフォールバック(代替フォント)の設定を確認します。
font-family: "Noto Sans JP", "ヒラギノ角ゴシック", sans-serif;
のように、複数のフォントを並べて指定しておくと、Webフォントが読み込めなかった場合でも似た書体で表示してくれます。私も最初はこれを忘れていて、通信環境の悪いスマホで「全然違うフォントで表示されてる!?」と焦ったことがありました。それ以来、必ず“保険フォント”をセットするようにしています。
③ ブラウザごとの見え方が違う
フォントの描画方法(レンダリング)はブラウザによって微妙に異なります。特にSafariはやや太めに、Windows版のChromeは細めに見える傾向があります。
私も一度、Macではきれいに見えていたのにWindowsでは「行間が詰まりすぎてる」と指摘されたことがありました。
それ以来、「Mac・Windows」「Chrome・Safari・Edge」のそれぞれでの見え方を必ず確認するようにしています。
④ 表示が遅い・読み込みが重い
日本語フォントはデータが重めなので、使うウェイト(太さ)を必要最小限に絞るだけでも大きく改善します。
私は以前、Light/Regular/Medium/Boldの4種類を全部読み込んでいたんですが、スマホで開いたときに明らかに遅くなってしまって…。結局、見出しと本文の2種類だけに整理したら、体感でページの読み込みがかなり軽くなりました。
代表的な人気Webフォントまとめ
ここでは、私がよく見かける・実際に使ってみて良かったと感じた、定番のWebフォントをまとめて紹介します。
どれも無料で使えるものばかりなので、まずは気軽に試してみるのがおすすめです。
■ ゴシック体
Noto Sans JP(Google Fonts)
Googleが提供している日本語フォントの中でも定番中の定番。
クセがなくて可読性が高く、本文にも見出しにも使いやすい万能フォントです。
企業サイトやブログなど、ジャンルを問わず安定して使えるので、私も最初に選ぶことが多いです。
M PLUS Rounded 1c(Google Fonts)
角がまるく、やわらかい印象のフォント。
やさしい雰囲気を出したいサイトにぴったりで、女性向けやカフェ系のデザインによく合います。
丸ゴシック系の中では特に読みやすく、Webでも使いやすいと感じました。
M PLUS 1p(Google Fonts)
シンプルでモダンな雰囲気のフォント。
「少しカッチリ見せたいけど堅すぎたくない」ときにちょうどいいバランスです。
オープンソースなので自由に使え、近年はコーポレートサイトでも採用が増えています。
■ 明朝体
Source Han Serif(源ノ明朝 / Adobe Fonts)
AdobeとGoogleが共同開発した本格派フォント。
字面がきれいで、行間の取り方にも品があります。
私は以前、会社案内ページの制作で使いましたが、信頼感を出したい場面にすごく合いました。
Noto Serif JP(Google Fonts)
上の源ノ明朝をベースにしたGoogle Fonts版。
無料で使えるのに完成度が高く、記事系のブログやメディアサイトでもよく見かけます。
落ち着いた印象にしたいときにおすすめです。
Shippori Mincho(Google Fonts)
クラシカルな雰囲気がありつつ、今っぽさも感じる明朝体。
少しやわらかい印象で、ポートフォリオサイトや個人ブログにも使いやすいです。
特にタイトルまわりに使うと、上品で印象的な雰囲気になります。
■ 欧文フォント
Roboto(Google Fonts)
GoogleがAndroid用に開発したフォントで、世界的に利用されている定番です。
無駄がなく読みやすいデザインなので、英語のUIやWebアプリ、コーポレートサイトなどに最適。
私は日本語フォントのNoto Sansと組み合わせて使うことが多いです。
Open Sans(Google Fonts)
文字のバランスがとてもよく、長文でも読みやすいフォント。
ニュースサイトやコーポレート系デザインでよく使われています。
シンプルですが堅すぎず、どんな日本語フォントとも相性が良いのが魅力です。
Montserrat(Google Fonts)
見出しに向いている、少しデザイン性のある欧文フォント。
スタートアップやクリエイティブ系のサイトでよく見かけます。
洗練された印象を与えたいときに使うと、全体がぐっと引き締まります。
まとめ
Webフォントを使うと、どの端末でも同じ書体で表示でき、デザインの世界観をきれいに統一できます。私も最初は難しそうに感じていたけれど、実際に使ってみると「フォントを変えるだけで、こんなに印象が違うんだ」と驚きました。
Google Fontsなどの無料サービスを使えば、コピペだけで簡単に導入できるので、初心者でもすぐに試せます。
“見た目を整える”というより、“サイトの空気を作る”のがWebフォントの役割。少しの工夫で、デザインがぐっとプロっぽく見えるので、ぜひ一度取り入れてみてください。

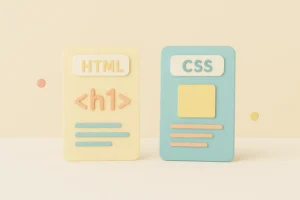
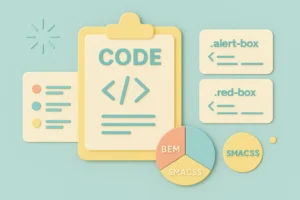

コメント